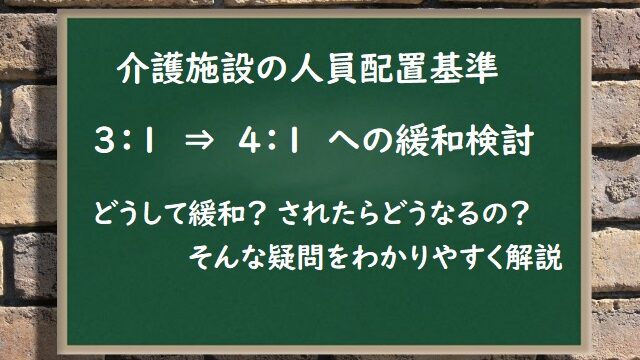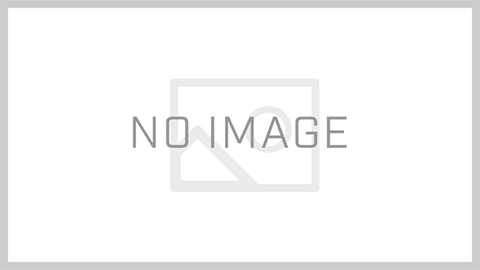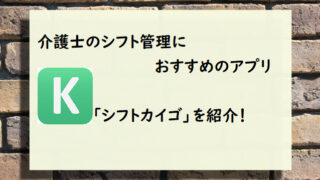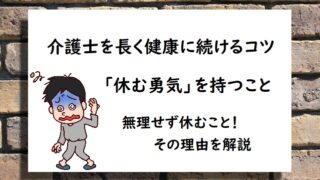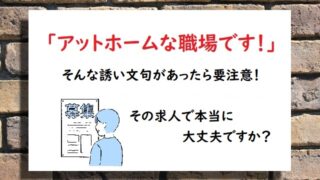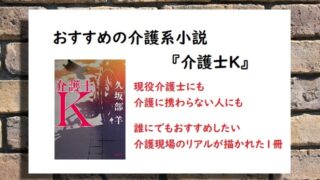事故報告書って聞くと嫌なイメージしかありませんよね。
「事故報告書、書かなきゃダメ?」
「事故報告書書くの面倒くさいな・・・」とか。
第一発見者になってしまった時なんかは「何で自分が書かなきゃいけないの?」と思ってしまう方も多いです。
他にもやらなきゃいけないこと沢山あるのに、事故報告書は経緯を確認したり、原因や対策を考える等手間のかかる業務内容です。ただ事故報告書など利用者の健康や命に関わる事案の報告書は書いておくことをおすすめします。
なぜなら
事故報告書は悪意や意図的なものによる事故を除いて、自分を守る道具になるからです!
ではなぜ事故報告書が自分を守る道具になるのか、これから解説していきます。
事故報告書を書く理由
名前の通り、事故が起きた時の状況などが記された報告書です。介護現場での事故は、利用者の転倒や怪我、誤薬、送迎車両の交通事故が多く、それらが起きたときに書きます。特に転倒と怪我は起きやすいためかその類の報告書が多いですね。
事故報告書を書く目的は大きく3つあります。
①再発防止のため
どういった経緯で原因でその事故が起きたのかを可能な限り分析して、同様の事故が今後起きない様に、介護の仕方や業務の在り方を再検討していくことが求められます。
職員の対応の問題なのか、介助方法の問題なのか、そもそも業務スケジュールやその時の職員の配置人数の問題なのかなど、問題点を見つけ出すことが再発防止には不可欠です。
職員全体で共有して同様の事故が起こりにくい環境に変えていくことで、職員にとっても利用者にとっても良い環境作りに繋げていくことが可能となります。
②事故の詳細や対応など正確な記録を残し、行政や家族などへしっかり説明できるようにするため
人間の記憶は時間が経てば経つほど曖昧になっていたり、美化されてしまうものです。事故の詳細を正確に記録に残すことができるのは、事故当日の対応したや発見した職員だけです。
行政や家族への報告も報告書があれば事故当時の経緯や対応などを正確に説明できると思いますが、思い出しながらの説明だったらどうでしょう?
順を追って説明しているつもりでも、後から「あ、そういえばさっきのあの時こうだったな、(こういう対応)したな」とか話の順がバラバラになり、理解しにくい説明になりやすいですし、報告内容が抜け落ちてしまうこともあるでしょう。もしそんなことが起きれば、行政や家族の不安感や不信感は増してしまいます。施設内だけでなく施設外とのトラブルを避けるためにも報告書は必要なものというです。
事故報告書がどう自分を守るのか?
自分を守る為のもの、と言ってもしっくりこないですよね。
報告書に事故の詳細や対応をしっかり書いておくことで行政や家族への報告を正確にでき、行政や家族の不安感や不信感を取り払うことができます。逆に正確な状況報告が行えていなかった場合、関わった職員の対応に不信感を持たれたり、施設の評価を落とすことにも繋がりかねません。
最悪のケース、訴訟に発展してしまうことも考えられます。
これまで介護現場での事故で訴訟に発展したケースは少なくありません。
どのような状況で事故が起きてどのように対応したのか、当時の業務環境下での職員の過失の有無を証明できる材料の1つが事故報告書ということになります。
通常の記録だけではなく、事故報告書を書くべき理由
事故報告書は書いた後に電子媒体か紙媒体で上司や他の役職、施設長などに回覧されますよね。でも介護の記録ソフトに入力する通常の記録の回覧をする施設ってあまりないですよね。(記録が紙媒体の施設の方には申し訳ありません・・・)
介護の記録ソフトの記録はいつでもだれでも編集できるものが多いので、悪意のある誰かに不利な編集をされてしまったり、不具合で記録が飛んでしまったりなんてことも考えられます。もしそんなことが起きれば事故に関する記録は無くなってしまい、関係者の曖昧な記憶だけになってしまいます。そうなればもう誰にも事故の正確な経緯はわかりません。
このことから事故の詳細の正確な記録を残すことができるのは記録ソフトよりも報告書ということになります。
事故報告書の書き方
報告書に書く内容は大体どこの事業所でも共通です。
①利用者名
②事故の発生日時、場所、事故の種類、状況、怪我の有無、利用者の様子など
③事故の経緯と原因(わからなければ考えられる原因)
④どのように対応したか
⑤再発防止、改善案
項目は意外と少ないのになんでこんなに面倒くさいんですかね・・・。この時のことどう書こうかな、とか私も未だに悩んだりします。
ここで書き方のコツについて解説します。
①誰が読んでも理解できるように書く
なるべく専門用語は使用せず、シンプルな文章で正確に伝わるように書いていくことが大切です。専門用語だらけだったり、だらだらと長い文章になってしまったりすると、結局何を伝えたいのかがわかりにくかったりと正確な情報が伝わらなくなってしまう可能性があります。
②客観的に書く
事故原因に対する言い訳などの私情を書いてしまうと自分を不利にしてしまうので、私情は抑えて報告書では事実を客観的に書くことだけに専念しましょう。客観的な内容にすることで読み手にも事故の詳細が伝わりやすくなります。
③5w1hで書く
いつ(when)・どこで(where)・誰が(who)・何をして(what)・どうして(why)・どのようにして(how)が報告で正確に伝えることができる基本です。
④事故の対応が終わってから、なるべく時間を空けずに書くこと
事故発生から時間が経てば経つほど、事故の記憶は曖昧になっていきます。自分がどのように対応して、利用者はどんな様子だったのかなど曖昧になっていき、本来、報告書に書くべき内容だった事実を見落としてしまうリスクがあります。
報告書作成に早く取り掛かれば、記憶も鮮明なので報告書も書きやすいと思いますが、時間が経ってしまうと「あの時どうしたっけ・・・」「利用者の様子とかどうだったっけ・・・」という状態になり、報告書作成にかかる時間も長くなってしまいます。
通常業務もやること沢山ありますし、面倒くさい報告書は記憶が鮮明なうちに片づけてしまうことをおすすめします。
最後に
事故に限らず、トラブルを避けるために報告書や確実な記録をとることはとても大切なことです。事故が起きてしまった時、事故が起きそうだった時、利用者や職員との何かしらの人間関係トラブルなど、後で正確な報告ができるようにするための記録は自分を守ることに繋がります。今回は「事故報告書」に限定した話をしましたが、正確な記録というのは報告書だけに限りません。録音や映像なども十分正確な記録に当たると思います。
認知症が進行してしまった高齢者や変な職員から突如難癖付けられたりということもあるかもしれません。今の介護現場では思いもしないような様々なトラブルが起きます。
自分と自分の人生を守るために、利用者さんの介護の質を低下させないために、今一度記録の重要性を見つめ直す機会となることができたら幸いです。